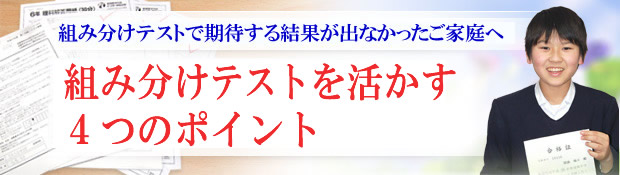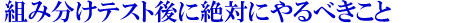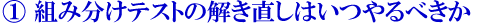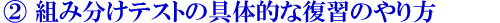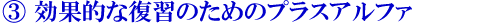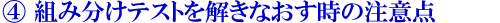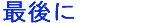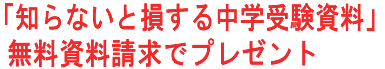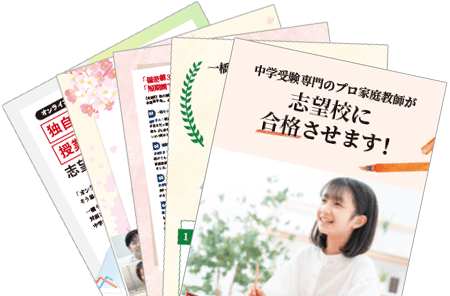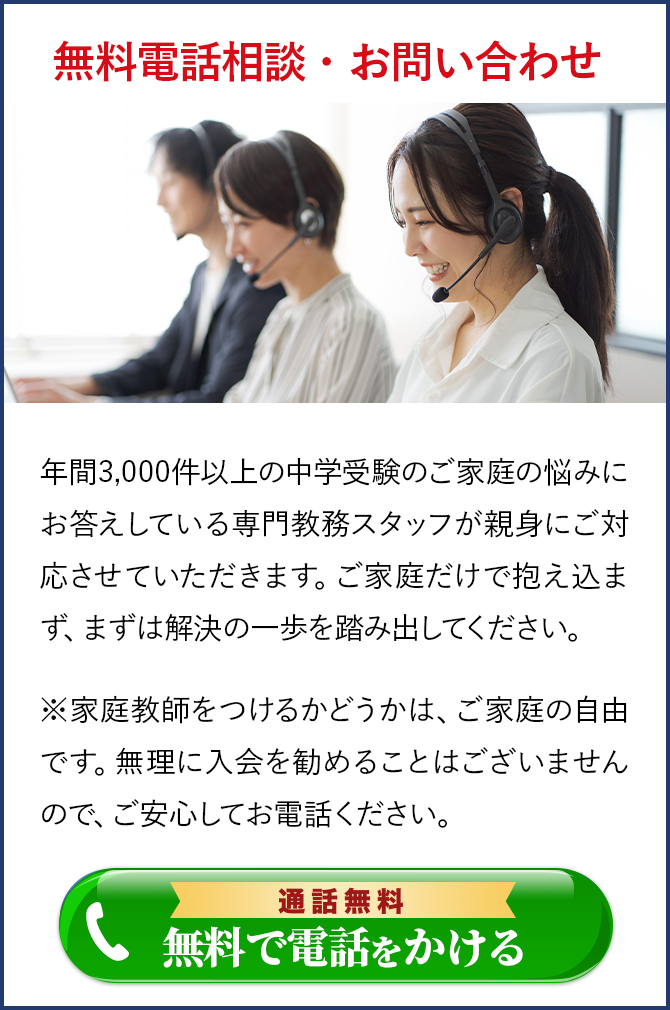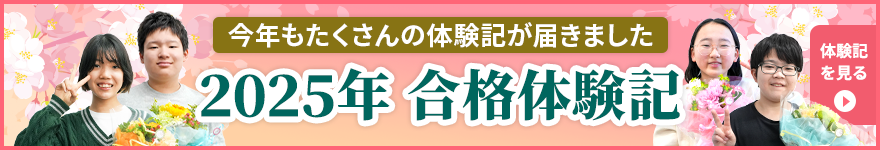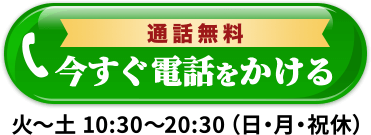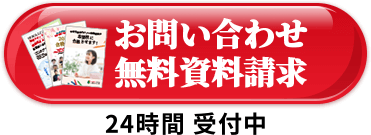- プロ家庭教師の一橋セイシン会 TOP >
- 組み分けテストを活かす4つのポイント
こんにちは、家庭教師の一橋セイシン会です
このページでは、前回のテストで期待する結果が出せなかったご家庭に、組み分けテストを活かすための4つのポイントを役立つ内容をお伝えします。
組み分けテストを受けた後に絶対にやるべきことは、「テスト」の復習です。
受験勉強においては「復習が大事」ということは、みなさんよくお分かりだと思います。
中学受験では、これまでに学習した内容の抜けや消化不良の単元をどれだけ穴埋めできるかが重要になります。
合否の分かれ目と言っても過言ではありません。
そして、お子さんの弱点を解消するのに「組み分けテスト」は最適なツールです。
もし、テストを受けっぱなし・解き直しが不十分というご家庭は是非、弱点克服ツールとしの活用法を学んでください。
組み分けテストを活用する場合、最も効果的なのは、終わったその日に復習することです。
どうやって解いたのか、お子さんの記憶が薄れないうちに、間違えたり解けなかったりした問題を確認することが重要です。
ただ、やらなければと思いつつも、塾の宿題が終わっていなかったりして、
なかなかそこまで手がまわりませんよね。
ですが、その日のうちに復習すると、
後で「どうやって解いたんだっけ?」と思い出しながら復習する場合よりも、
ずっと少ない時間と労力で、振り返ることができます。学習効果もより高くなります。
次に、組み分けテストを活用した具体的な復習のやり方についてお話しします。
組み分けテストの振り返りは大事と頭では分かっていても、やるべきことは多いため、 あれもこれもやるわけにもいきませんよね。
そこで、次の2つに絞って解き直します。
① 不正解の問題
② 正解したけれど、「なぜそうなるのか」を説明できない問題
②の『正解したけれど、「なぜそうなるのか」を説明できない問題』は、理解しきれていない、あるいは、まぐれ正解の問題です。そういった問題は、時間が経ったり、見た目がちょっと変わったりすると、解けないこともあります。
ですので、不正解の問題だけでなく、説明できない問題も解き直すようにしましょう。
効果的に復習するためには、同じ問題が解けるようになった後に、類題を解いてみることが大切です。
記憶力の良いお子さんだと、問題を丸暗記してしまうことがあります。 理屈をきちんと理解できているかをチェックするには、「類題」を解くことが必要です。
また、あまり時間が経つと、「元の問題をどのように解いたのか」を忘れてしまいます。 なるべく記憶が新しいうちに解いてみるのがポイントです。
できれば当日に、無理なら1週間以内に類題演習を行いましょう。
類題を探すときは、模試の解説を見てみましょう。
どの単元の問題だったか記載されていることが多いので、
普段使っているテキストと照らし合わせると類題を探すことができます。
最後に、組み分けテストを解きなおす時の注意点についてお話しします。
テストを解きなおす時にやってはならないことがあります。
「極端に正答率が低い問題」
「現状に対してレベルの高い問題」
の復習に時間をかけてしまうことです。
これらの問題は、×印をつけてあげて、しつこく追わないようにしてあげることが大切です。
お子さんに必要ない問題に時間をかけないようにしましょう。そうすれば、抜けている部分や弱いところだけに集中できるので、より効率的に復習できます。
いかがでしたでしょうか?
とても大変そうに感じた方もいらっしゃるかと思いますが、組み分けテストの解き直しをそこまで行うことが、必ず次に繋がります。
今回ご紹介した4つのポイントを参考に、次の組み分けテストに向けての準備をしていきましょう。
また、一橋セイシン会では、組み分けテストに限らず、中学受験で成功するためのノウハウをご紹介しています。 気になる方は、まずは無料の資料請求をしてください。「知らないと損する中学受験資料」を丸々一式お送りいたします。