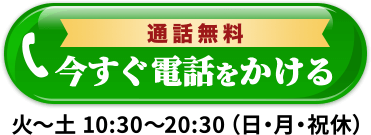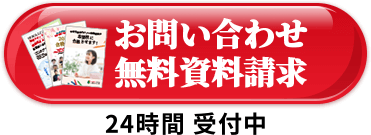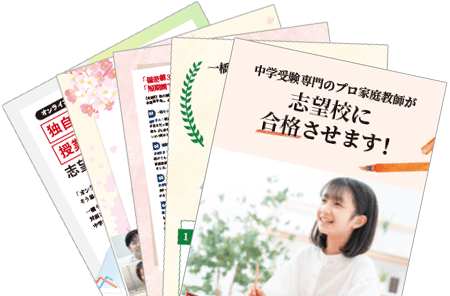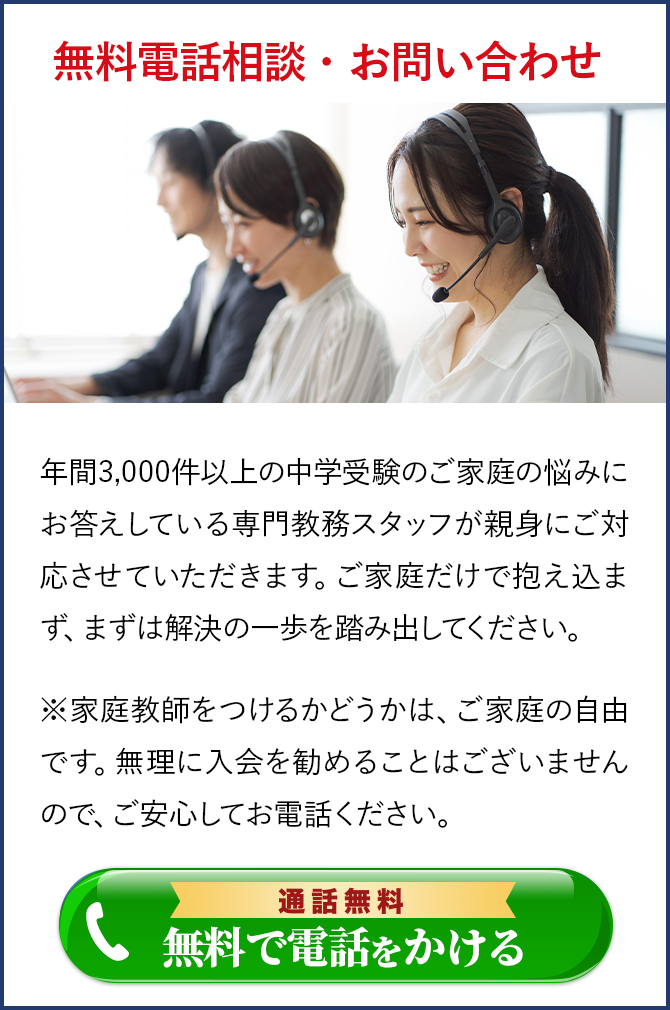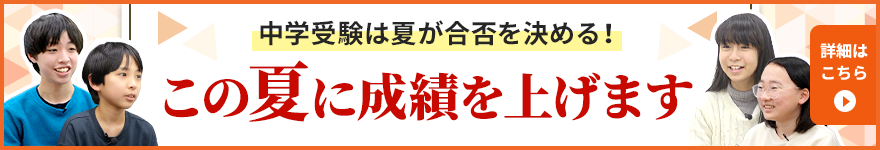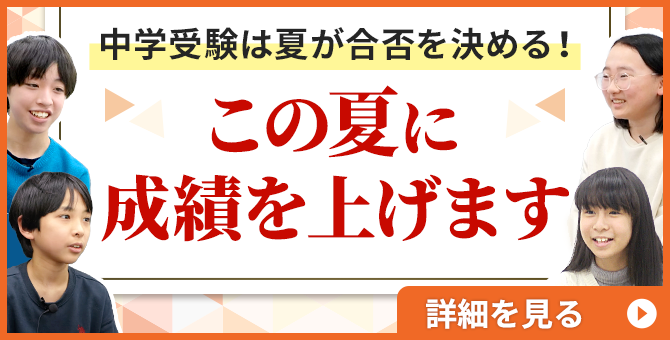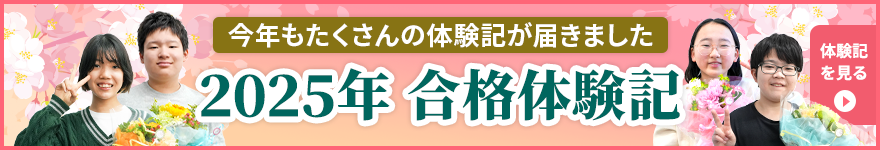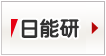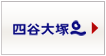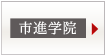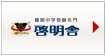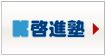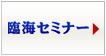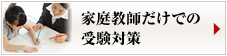- 中学受験専門 家庭教師の一橋セイシン会
- > 桐朋中 対策サイト
- > 理科対策
桐朋中学校
-理科の入試傾向と合格対策-
このページでは、桐朋中学校の理科の入試傾向と対策ポイントについて解説しています。
どうすれば桐朋中学校の理科を解けるようになるのか、合格点を取れる志望校対策のポイントを具体的に解説していますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。
| 桐朋中学校 理科 2023年入試データ | |
|---|---|
| 配点 | 60点 |
| 試験時間 | 30分 |
| 大問数 | 4題 |
| 頻出分野 | 生命、物質総合、エネルギー、地球・月・太陽系など |
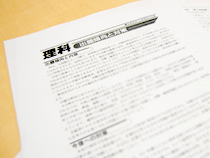
桐朋中学校 理科の入試問題の傾向
桐朋中学校の理科の出題分野を見ると、特定の分野・単元に偏りがなく、4分野から様々な単元が出題されています。
設問形式を見ると、記号選択問題が多めですが、記述問題、計算問題、作図問題など、多様な設問が見られます。表やグラフ、図からデータを読み取る、いわゆる「読み取り問題」も頻出です。
桐朋の理科は点差が大きく開きにくい傾向にありますので、誤字や計算ミスなどのケアレスミスには十分な注意が必要です。
桐朋中学校 理科で合格点を取る対策ポイント
桐朋中学校の理科で出題されるのは、単なる知識問題ではなく、実験・観察・観測を取り上げた問題が中心です。問題集や過去問でできるだけ多くの問題に触れておきましょう。
また桐朋中学校の理科で大きな比重を占める、グラフや表の読み取りと計算を必要とする問題です。
たとえば、過去の問題で「魚の大きさと、エサの消化時間」についての問題が出されました。きさが違う4匹の魚の消化時間が、エサの重さによってどのように変化するか表したグラフに基づいて答える問題です。
このような問題は知識の丸暗記では太刀打ちできないので、「グラフや表を読み取り、分析する力」と「正確な計算力」を養っておくことが不可欠になります。
桐朋中学校の算数で合格点を取るには、こうした入試問題の傾向を踏まえた上で、志望校対策を講じていくことが必要です。