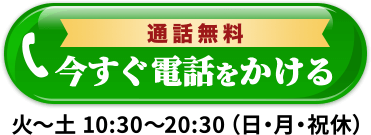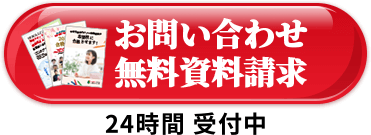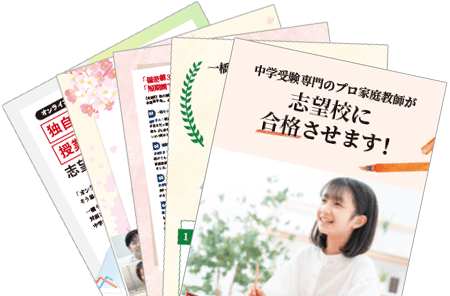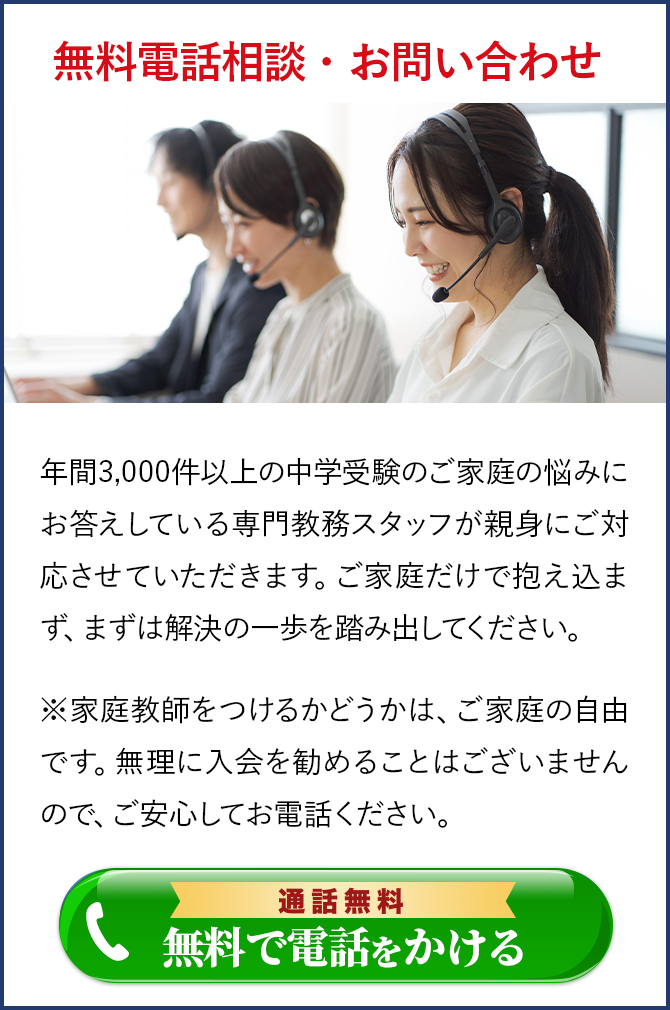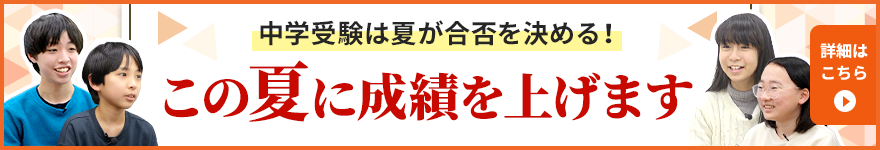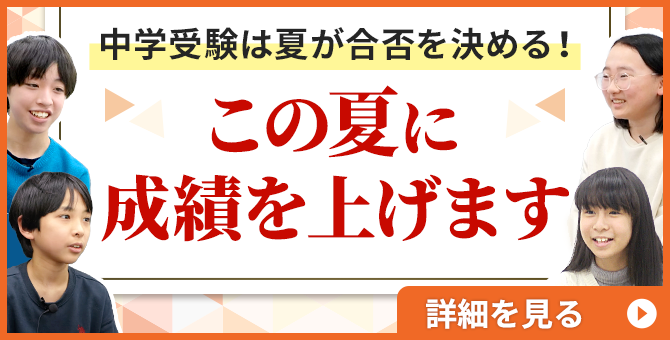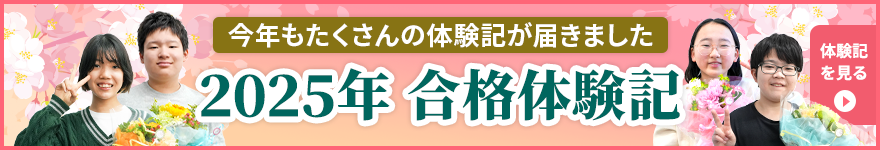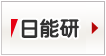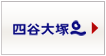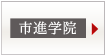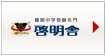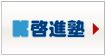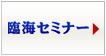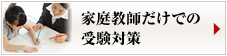- 中学受験専門 家庭教師の一橋セイシン会
- > 立教新座中 対策サイト
- > 理科対策
立教新座中学校
-理科の入試傾向と合格対策-
このページでは、立教新座中学校の理科の入試傾向と対策ポイントについて解説しています。
どうすれば立教新座中学校の理科を解けるようになるのか、合格点を取れる志望校対策のポイントを具体的に解説していますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。
| 立教新座中学校 理科 2023年入試データ | |
|---|---|
| 配点 | 50点 |
| 試験時間 | 30分 |
| 大問数 | 4題 |
| 頻出分野 | 各分野からまんべんなく出題 |
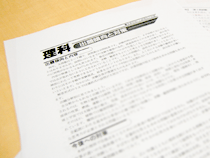
立教新座中学校 理科の入試問題の傾向
出題レベルは高いが、易化傾向も
立教新座中学校の理科は、ここ数年、試験時間30分に大問4題という出題構成が続いています。総設問数は30~40問の間でしたが、近年は減少傾向にあります。2023年は30問でした。中学入試の理科のなかでも、難度が比較的高いのが特徴です。
「記号選択」から「グラフの作成」まで、多様な設問
解答形式を見ると、記号選択が中心ですが、2017年にはグラフの作成など、様々な形の問題が出されています。記述問題は例年あまり見られず、2017年、2018年、2019年と出題されていませんが、復活する可能性もあるので、どのような問題でも対応できるよう、多くの問題を解いて、演習を積んでおくことが求められます。
出題分野は幅広い、実験・観察問題がほとんど
出題分野については、大きな偏りはなく、「生物」「化学」「物理」「地学」分野から、まんべんなく出題されています。過去には、生物分野からは「メダカの成長」「動物のからだのつくり」「動物の行動」「植物の蒸散」「消化のはたらき」「食物連鎖」、化学分野からは「ものの燃え方」「水溶液の中和反応」「水の状態変化」「気体の発生と性質」、物理分野からは「力のつり合い」「電気」「磁石」、地学からは「月食と月の満ち欠け」「星の動き」「地層と岩石」などが取り上げられました。
実験・観察問題が多く、計算問題や実験器具の使い方を問う問題も出題されています。
立教新座中学校 理科で合格点を取る対策ポイント
難度の高い「記号選択問題」に注意
立教新座中学校の理科は、記号選択式の問題が中心です。記号選択というと、難度が低いように思われがちですが、立教新座中学校の場合、選択肢が多かったり、「全て選ぶ」形式の問題であったりと、正確性を求められる難度の高い問題が少なくありません。丸暗記する勉強法ではなく、普段から授業を理解し、油断せずに、過去問で問題形式によく慣れておきましょう。
「実験・観察問題」の攻略が合格のカギ
立教新座中学校の理科で合格点を取るポイントは、比重の大きい「実験・観察問題」の攻略にあります。実験・観察問題を解くには、知識の「丸暗記」では太刀打ちできません。理屈や過程をしっかり理解した上で、多くの問題を解いて、知識を「使える」ようにしておくことが必要になります。
目新しい題材の問題も・・・
立教新座中学校の理科の実験問題では、2019年に「電池と豆電球と電流を用いた実験」について出題されました。様々な実験に関する問題が出題されていますが、今までに学習した内容を使えば、十分解くことができます。こうした応用問題の対策をする際には、普段から少し難しいレベルの問題に取り組んで、解き方をじっくり考えるようにしていくことがポイントになります。
志望校対策はレベルの高い問題を中心に
また、立教新座中学校の理科は、先述の通り平均点に波はあるものの、偏差値のわりに難度が高いです。立教新座中学校の志望校対策をする際には、応用レベルの問題や、少し偏差値が高めの学校の過去問で演習を繰り返しながら対策をするのが効果的です。
立教新座中学校の理科で合格点を取るには、こうした入試問題の傾向を踏まえた上で、志望校対策を講じていくことが必要です。